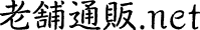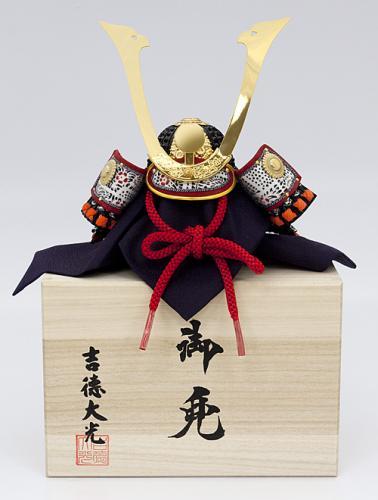コレクション: こどもの日
こどもの日こと、端午の節句とは?五月人形以外に何を準備すべき?
今回は初夏の行事、端午の節句についてご説明いたします。

◆端午の節句とは
端午の節句は5月5日に、男の子の健やかな成長を祝う行事です。
菖蒲やよもぎを軒に吊したり、菖蒲湯に浸かったりすることで無病息災を願ったため、「菖蒲(しょうぶ)の節句」とも言われます。
◆端午の節句の由来
中国の楚からはじまり、日本の「五月忌み(さつきいみ)」という風習と結びついたものと考えられています。
五月忌みは女性の節句でしたが、鎌倉時代頃から、「菖蒲」が武勇を重んじるという意味を持つ「尚武」と同じ読みであることや、菖蒲の葉が剣に似ていることから、男の子の節句とされるようになりました。
◆端午の節句の風習
端午の節句には、鎧や兜、刀、武者人形や金太郎などを模した五月人形を飾り、鯉のぼりを立てます。
また、初節句にはちまきを、2年目以降は柏餅を食べるという風習があります。
鎧には身を守るという意味が、鯉のぼりには立身出世の願いが、柏餅には家系が絶えず続くという意味が込められています。
特に初節句は、ゴールデンウィークの最中ということもあり、親族総出で祝うことも多いようです。鎧兜は昔は祖父や父といった男性が飾っていましたが、今は特にこだわる必要もないようです。
飾りの準備は4月中旬頃までに行い、5月5日の当日または前日に親族や知人を招き、縁起のいい料理でもてなします。
-
人形町志乃多寿司總本店 志乃多のいなりあげ
通常価格 ¥411通常価格単価 / あたり -
秋色庵大坂家 秋色最中(ハートの焼印:5個入)
通常価格 ¥1,100通常価格単価 / あたり -
人形町志乃多寿司總本店 ちらし寿司の素
通常価格 ¥864通常価格単価 / あたり -
人形町志乃多寿司總本店 志乃多の煮かんぴょう
通常価格 ¥381通常価格単価 / あたり -
いせ辰 江戸犬張子七番
通常価格 ¥17,600通常価格単価 / あたり -
いせ辰 江戸犬張子六番
通常価格 ¥19,800通常価格単価 / あたり -
いせ辰 江戸犬張子五番
通常価格 ¥24,200通常価格単価 / あたり -
【完売御礼】いせ辰 手ぬぐい 江戸犬張子 其の一
通常価格 ¥1,650通常価格単価 / あたり -
いせ辰 江戸犬張子一番
通常価格 ¥49,500通常価格単価 / あたり -
いせ辰 壁掛け犬張子
通常価格 ¥2,420通常価格単価 / あたり -
いせ辰 江戸犬張子三番
通常価格 ¥38,500通常価格単価 / あたり -
【完売御礼】いせ辰 手ぬぐい 江戸犬張子 其の二
通常価格 ¥1,650通常価格単価 / あたり -
いせ辰 うちわ江戸柄 大判 犬張子
通常価格 ¥3,850通常価格単価 / あたり -
いせ辰 江戸犬張子八番
通常価格 ¥14,300通常価格単価 / あたり -
秋色庵大坂家 秋色最中(ハートの焼印:10個入)
通常価格 ¥1,800通常価格単価 / あたり -
いせ辰 壁掛け犬張子 黒
通常価格 ¥2,750通常価格単価 / あたり -
今朝 松阪牛A5ロース肉すき焼具材セット2人前 冷蔵 黒化粧箱入り
通常価格 ¥23,760通常価格単価 / あたり -
 売り切れ
売り切れ【在庫切れ】いせ辰 江戸犬張子末広
通常価格 ¥33,000通常価格単価 / あたり -
いせ辰 江戸犬張子力犬素張り
通常価格 ¥6,600通常価格単価 / あたり -
黒江屋 子供用 木製 漆塗 スプーン すぷーん どうぶつえん
通常価格 ¥3,080通常価格単価 / あたり -
いせ辰 人形祝儀袋 犬張子
通常価格 ¥880通常価格単価 / あたり -
吉徳 犬張子 ざるかぶり
通常価格 ¥2,750通常価格単価 / あたり -
今朝 すき焼用 松阪牛5ロース肉2人前(360g)冷凍 黒化粧箱入り
通常価格 ¥21,600通常価格単価 / あたり -
吉徳 ゴールデンレトリバー Sサイズ
通常価格 ¥3,960通常価格単価 / あたり -
いせ辰 江戸犬張子力犬
通常価格 ¥6,050通常価格単価 / あたり -
【在庫切れ】吉徳 幸福大熊猫 シンフー・パンダ L
通常価格 ¥5,500通常価格単価 / あたり -
黒江屋 子供用 木製 漆塗 お箸 おはし おはな
通常価格 ¥1,980通常価格単価 / あたり -
黒江屋 子供用 木製 漆塗お椀 こわん どうぶつえん
通常価格 ¥6,050通常価格単価 / あたり -
黒江屋 子供用 木製 漆塗お椀 こぼーる どうぶつえん
通常価格 ¥5,720通常価格単価 / あたり -
吉徳 特製小型兜(桐箱入り)「大鍬形」11号 114672
通常価格 ¥19,800通常価格単価 / あたり -
吉徳 特製小型兜(桐箱入り)「長鍬形」11号 114671
通常価格 ¥19,800通常価格単価 / あたり -
山本海苔店 はろうきてぃ海苔ちっぷす2缶セット(うめ・ツナマヨ)
通常価格 ¥1,728通常価格単価 / あたり -
黒江屋 子供用食器 こぼん くるま
通常価格 ¥6,050通常価格単価 / あたり -
黒江屋 子供用食器 すぷーん くるま
通常価格 ¥3,080通常価格単価 / あたり